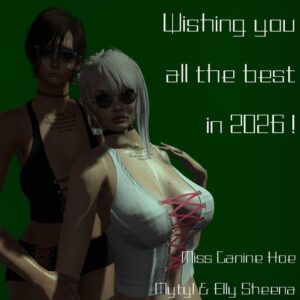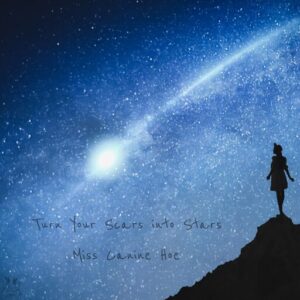正確にはきっと「応答の『手前』」。
先月末、Elly と横浜でのんびりと二泊三日を過ごした。
また時間の感覚が二人してバグってしまって面白かったけれど。
Elly の親友で、わたしたちが二人で活動を開始した当初からコメントなどを寄せてくださっていた K さんとも(やっと!)お目にかかって、非常に刺激的なお話をすることができたし、Y さんがご招待くださった KT Zepp 横浜でのライブも満喫させていただいた。
その数日後にライブに出していただいたわけなんだけれども。
K さんの影響で、ライブの準備や仕事の傍ら、佐々木健一『美学への招待 増補版』(中央公論新社・2019)を読み進めていて。昨日?一昨日?にようやく読み終えた。
一気に読める本と読めない本があるけれど、これは後者で。
一章読んでは本を置いてウンウン唸りながらいろいろ考えて。またちょっと経ってから開いて続きを読んで……の繰り返しで、薄い本だけれどずいぶん時間がかかった。
ライブについての投稿で、
SACHI FUKUHARA さんと那須真吾さんには、中山肇さんとのパフォーマンスを拝見して抱いた「言葉にならない感動」を無理やり言葉にして、控え室で喚き散らかした
と書いたんだけれども、この「言葉にならない感動」についてずっと考えていたというか、頭から離れてくれないので考えざるを得なかったというか、そんな感じでいて。
で、上述の書籍の増補された部分を読んで、ちょっと腑に落ちたような気もしなくもないような感じに頭の中が変化したので、とりとめなくまとめてみようかと思ってこれを書いている。
ものすごく乱暴に言ってしまうと、
19 世紀までは芸術の当然の前提と考えられていた、つまり芸術には内包されているものと誰も信じて疑わなかった「美」が、20 世紀に入って(スプラッタ映画さながらに)芸術から引きずり出され、投棄されてしまう。その後、同世紀末に「美」は「復権」を果たしていくわけだが、もはやそれは(「復権」であるがゆえに)所与の前提とはなり得ず、なぜ芸術には「美」が必要なのか、そもそも「美」とは何なのか、という問いが立てられることになる。
というのが上述書の増補部分(の一部)の概要……こういう理解で合ってるのかな。
その後、この問いに真っ正面から向き合った二人の哲学者、ダントーとネハマスの学説が紹介されていく。
この箇所に限らず、とてもスリリングな本だと思うので、ご一読をオススメしたいのだけれども、それは置いておいて。
わたしは「美学」についてこの本で初めてその端っこに触れたくらいの、初心者とも言えないくらいのずぶの素人なので、偉そうなことは言えないし、言う気もないけれど、芸術と呼ばれる世界の周縁でちまちまとその一隅を汚しているくらいの自覚はあるので、どうしたってその中心にそびえ立つ(あるいは、再びそびえ立った)「美」とは何なのかについては考えてしまうわけで。
いわゆる近代芸術を「美しい」と思ったことがあまりなくて、むしろ「美」的には抜け殻でしかない(ことになっている)現代芸術にどうしようもなく惹かれてしまうから、感じなくてもいいと頭のどこかでは分かっていても、別のどこかで引け目を感じていて。
わたしが感じない何かを他の人たちは感じているのだとしたら、それはいったいどんなものなのだろうと、ずっと気になっている。
ただ、それはきっと、「この絵を見て/この音楽を聴いて、あなたは何を美しいと感じるの?」と誰かに問い、その答えを聞いて感得できるようなものではないだろうというのは、もはや確信に近いものとしてある。
この色が、この形が、この光が、この闇が、このリズムが、このメロディが、このハーモニーが……といくら語られても、それらの言葉は、わたしと相手の間にぽっかりと口を開けた、深くて暗い穴に吸い込まれていくだけ。
空の青さ一つ満足に言葉にできないわたしたちに、「美」を言葉で交換することは不可能だろうという予感は、子どもの頃から持っているし、歳を重ねるにつれて、その予感は確信に変わりつつある。
何でこんなことをつらつらと書いているかというと、先日出演させていただいたライブで拝見した、中山肇さん・SACHI FUKUHARA さん・那須真吾さん・Soma さんのパフォーマンスに、圧倒的な「美」を感じてしまい、そしてそれはやはり「言葉にできない感動」としか言えないものだったから。

わたしたちは言葉でしかものを考えられないし、言葉にできないものを蓄えることも他者と交換し合うこともできない。
しかし、わたしたちは、少なくともわたしは、何かを見たり聴いたりして、それが評価としての、あるいは「応答」としての言葉に変換されるプロセスの中に、その変換の手前に、前駆体のような、「言葉になる前の何か」があるような気が、ずっとしている。
図で描いてみたらこんな感じ。

②に至る、つまり解釈され、言語によって応答される前の①の段階。黄色い雲みたいなので、「言葉になる前の何か」を図示しているつもり。
そして、「美」は①の段階でのみ感得される(①の枠の外に出た時点で失われている)のではないか、というのが、件のパフォーマンスにひたすら感動し嘆息することしかできなかったわたしが、現時点で立てている仮説。
②に至ろうとするわたしの意識の、半ば自動化された活動を阻むように、次から次へと押し寄せてくる「名状しがたい何か」にわたしはただただ圧倒され、殴られながら抱きしめられているような感覚に翻弄されているだけだったし、今でもまだそこから脱し切れてはいない。
[追記]
堀内彩虹「〈自己〉を聞く技法としての演奏行為」(『ユリイカ 令和 5 年 12 月 臨時増刊号』・青土社・2023・p.198)にはこう書かれている。
……言語的規定を逃れるがゆえに、概念化の過程では言語に掬いとられなかったであろう……余剰もが捨象されることなく……刻み込まれている
でも、その感動と嘆息はどうしても伝えたくて、先ほどの引用のように控え室でお二人に喚き散らかしたり、那須さんと中山さんが一緒にいる時に喚き散らかしたり、打ち上げで中山さんに喚き散らかしたりしてたわけで。
何言ってるか分からなかったと思うんですよね……自分でも言葉にできないこと(①)を口から出してるわけだから。
わたし自身、口を開けば開くほどじれったくて、じれったいから何か言葉を付け足したくなって、それは必ずどこか的外れで……っていう状態だったし。
書いていて思ったけれど、那須さんや FUKUHARA さんの身体表現もまた、中山さんの音やお互いの身体表現に対する「応答」であるはずで。
その応答は①なのか②なのか……すごく気になる。両方なのかなあ。
舞踏なりジャグリングなりを自らの表現手段とするということは、②の段階まで進んだ理解や訓練に基づいた、少なくともそれを土台とした身体の動きをわたしは見ていたわけだけれど、息を呑んだのは、中山さんの音が変わるか変わらないか、そのほんの小さなあわいで、お二人の動きがスッと変わったこと。
音が変わってから動きが変わるのなら、なんだろう、理解の範疇の内側というか、そうだよねっていう感じというか、頭で分かるという気がするんだけれど、その一瞬手前ですべてが変わるという、大げさに言えば奇跡のような瞬間を目の当たりにしてしまったわたしは、時間が止まったような感覚にすら襲われていて。
こうして言葉を費やせば費やすほど、何かから遠ざかっていくような奇妙な脱力感があるので、ここら辺でやめておく。やっぱりちっともまとまらなかった。
「美」の追求に囚われすぎて身動きできなくなることは避けたいけれど、「美」と「快楽」の関係性、それらの共通点や相違点を探っていきたいという思いもある。
どちらかというと音は後者に近づく傾向がある気もするし、後者でありつつ前者でもあることが十分可能だというのは、K さんとの対話やこないだのライブで(文字通り)身をもって知ったわけだから、次はそれを……
次はそれを、わたしはどうしたいんだろう?
[追記]
この投稿を読んでくださった K さんが、佐々木健一『美学事典』(東京大学出版会・1995)からの引用を LINE でつたえてくれた。
対象を美と判断する働きの特徴をカントは、想像力と悟性の調和的な遊動のなかに見た
読んでハッとしたのは、「想像力」という、わたしにとって最も大切なキーワードの一つが、この考察のなかですっかり抜け落ちていたことに気づいたから。
「調和的な遊動」説に賛成はできないけれど、想像力が発揮され終わる前、その発揮の「最中」の状態を①だと考えてみることはできそうな気がする。